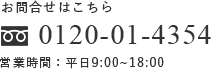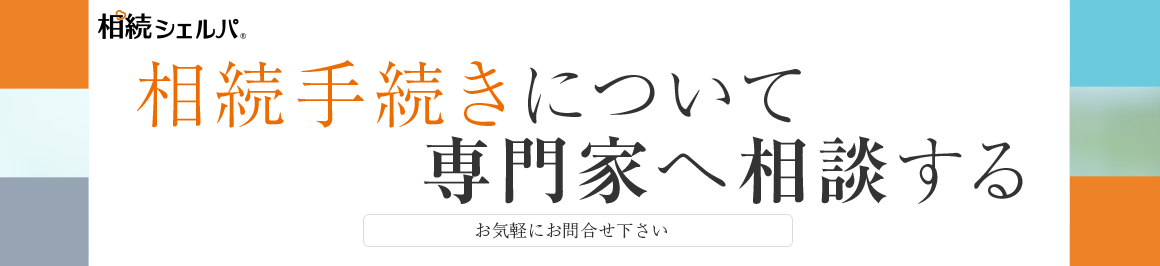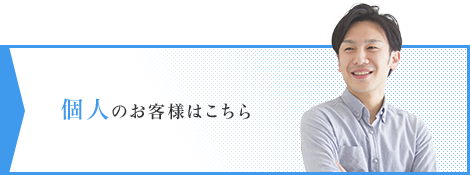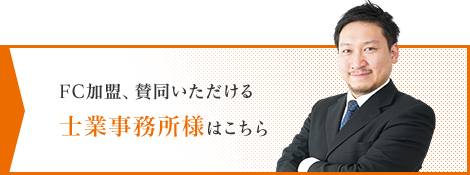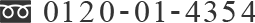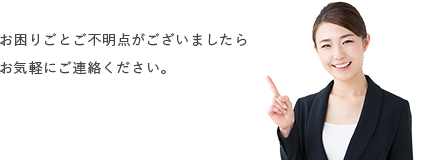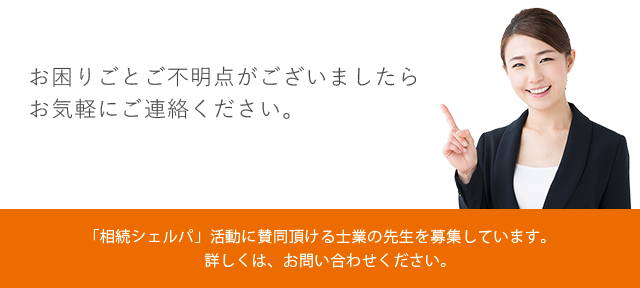2021.2.21
祖母から孫への相続について
相談内容
よろしくお願いします。
祖母の持つ財産についての質問です。
祖母には、娘(私の母)が居ますが、放蕩者で常に祖母に対して金銭を要求しており、祖母も長いこと支払いをしてきました。証拠がある分だけで500万程、実際にはそれ以上になると思います。
この度、祖母が高齢ということもあり、財産についての話で「孫ふたりに全て分けたい」と言われました。孫1は、祖母から見て長男の子どもにあたり、長男は既に他界しています。孫2の私は今のところ相続の権利は持っていないことになるかと思います。
早いうちにまず株だけでも孫2人に分けようと祖母が動いています。自分なりに調べてみると、生前贈与したとしても、一定の期間は遺留分が発生することなどを知り、遺言書を残しても、申し立てをされれば相続を受ける権利があることを知りました。
祖母としては何としても娘(私の母)に遺産が渡ることを嫌がっています。
遺言書を作る。相続の廃除などを考えておりますが、廃除は難しいとも聞きました。
できるだけ祖母の希望(孫2人に全ての遺産を受け継ぐ)を叶えるために、どのような手続きが必要でしょうか。
祖母の財産は、株券が約6000万円分と預貯金400万程あります。
どうぞよろしくお願いします。
祖母の持つ財産についての質問です。
祖母には、娘(私の母)が居ますが、放蕩者で常に祖母に対して金銭を要求しており、祖母も長いこと支払いをしてきました。証拠がある分だけで500万程、実際にはそれ以上になると思います。
この度、祖母が高齢ということもあり、財産についての話で「孫ふたりに全て分けたい」と言われました。孫1は、祖母から見て長男の子どもにあたり、長男は既に他界しています。孫2の私は今のところ相続の権利は持っていないことになるかと思います。
早いうちにまず株だけでも孫2人に分けようと祖母が動いています。自分なりに調べてみると、生前贈与したとしても、一定の期間は遺留分が発生することなどを知り、遺言書を残しても、申し立てをされれば相続を受ける権利があることを知りました。
祖母としては何としても娘(私の母)に遺産が渡ることを嫌がっています。
遺言書を作る。相続の廃除などを考えておりますが、廃除は難しいとも聞きました。
できるだけ祖母の希望(孫2人に全ての遺産を受け継ぐ)を叶えるために、どのような手続きが必要でしょうか。
祖母の財産は、株券が約6000万円分と預貯金400万程あります。
どうぞよろしくお願いします。
回答
ご質問ありがとうございます。行政書士法人エベレストの野村篤司と申します。以下、一般的な法制度についてご紹介のうえ、回答させ